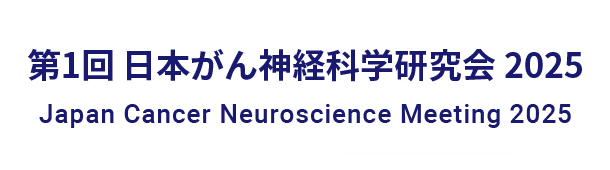- HOME
- お知らせ
川内教授が参画したキュリー研究所との国際共同研究がCancer Cellに掲載されました。
2026.01.15 最近の研究活動
Multiomic integration reveals tumoral heterogeneity of lipid dependence within lethal Group 3 medulloblastoma
論文はこちら
元博士研究員の白石君、大学院生の王君と一緒に参画した国際ネットワークによる脳腫瘍マウスモデルのDNAメチル化解析がNature Geneticsに掲載されました。
2025.12.11 最近の研究活動
この研究は、世界中の脳腫瘍マウスモデル開発の専門家たちが所有するモデルのDNAメチル化をドイツがん研究センターのプラットフォームでEPICアレイを用いて解析し、比較した大規模な論文です。検体の収集から5年の大作で、川内教授がドイツPI時代に指導した元博士課程学生のTuyu Zhengさん(現StJude小児研究病院 博士研究員)が筆頭著者の一人になっています。
論文はこちら
川内教授とチャップマン助教が日本脳腫瘍学会で発表しました。
2025.12.07 最近の研究活動
川内教授が「ZFTA 型上衣腫における L1CAM-YAP1 経路に着目した機能解析と前臨床評価」
チャップマン助教が「小児脳腫瘍における染色体外 DNA 増幅の腫瘍間多様性」で発表を行いました。
第一回がん神経科学研究会を名市大にて開催しました。
2025.10.18 新着情報

120人を超える参加者に来ていただき、白熱した議論やネットワーキングが行われました。
この分野の今後の発展を確信しました!来年は東京・国立がんセンターで10/10の開催になります。(川内)
大学院生の王君と執筆した髄芽腫マウスモデル作製の方法論がNature Publishing GroupのeBook「Neuromethods」に掲載されました。
2025.10.05 最近の研究活動
我々が髄芽腫研究において利用している体細胞変異によるマウスモデル作出技術を共有したいと思い、Duke大学の友人Michael Goldsteinから依頼を受けて執筆しました。脳腫瘍研究に多くの分野の方が興味を持っていただけると嬉しいです。詳細はこちら
川内教授の研究提案が公益財団法人大幸財団の2025年度自然科学系学術研究助成に採択されました。
2025.09.09 新着情報
採択された研究費の内容をご紹介します。今回の研究提案は、腫瘍進展のメカニズムについて知見が限られている Grp4髄芽腫 を対象としています。私たちは、最近開発した N1-SRC誘導型の新しいがんモデル と 患者由来異種移植(PDX)モデル を駆使し、腫瘍細胞とニューロンの相互作用を解析することを目指しています。
Grp4髄芽腫は 神経系の遺伝子シグネチャー を示すことから、がんと神経細胞との関連が強いと考えられます。本研究を通じて、仮説に基づく新たな分子機構の発見につながることを期待しています。
大学院生の肖君が参画した稲垣先生(NAIST)との共同研究がAdvanced Science (IF:14.1)に掲載されました
2025.08.14 最近の研究活動
肖君は脳オルガノイドを用いてヒト膠芽腫細胞の細胞移動にSHTN1が寄与していることを証明しました。
脳オルガノイドの樹立はNCNP青木吉嗣部長の協力で行いました(Xiao et al. in preparation)。
この研究はYahoo JAPANなどのニュースでも取り上げられています。